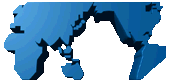| ちょっと勉強してみませんか、フランス語の数の体系、 フランス語使用、フランス語教育の現在 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 次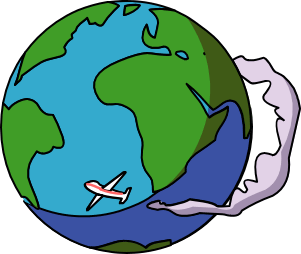 ルッソン 0 : 石原都知事のおっしゃる「フランス語」 ルッソン 1 : 60+10、4×20の由来――英語にもあった20進法 ルッソン 2 : フランス語を使用している国と地域 ルッソン 3 : 「フランコフォニー」の簡単な年譜 ルッソン 4 : 一体、世界のどのくらいの人々がフランス語を使っているのか? ルッソン 5 : 日本ではどのくらいの人々がフランス語を学んでいるか? ルッソン 6 : 石原都知事仏語発言に関する海外メディアの反応 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルッソン 0 : 石原都知事のおっしゃる「フランス語」 石原東京都知事――「フランス語は数を勘定できない言葉で・・・」 >> いうまでもなく、できます。 石原東京都知事――「〔フランスは〕過剰に自国語に自信を持ち過ぎて、ろくに数の勘定ができないフランス語というのは、やっぱり国際語として脱落していきました」「国際語として失格しているのも、むべなるかな」「かつて外交官の公用語としてフランス語というのは幅をきかせたけれども、世界が狭くなっていろいろな問題が出てきてね。〔・・・〕そういうことから〔フランス語は国際語として〕だんだん外れていったんですよ」 >> フランス語は、現在、世界60カ国以上の国々で話されています。 >> フランス語は、国連公用語の一つです。 >> フランス語は、英語とならぶ国際オリンピック委員会(IOC)の公用語で、IOCのすべての会議は英仏二カ国語で運営されています。東京都がオリンピック開催地に立候補するくらいですから、もちろん、都も都知事も、このことは御存知でしょう。 >> 国際郵便条約では、フランス語が正文と定められています(以下、税関の「票符」参照)。 >> こんなこと、逐一列挙するのもバカバカしいくらいですよね。
石原東京都知事――「タヒチとか、かつてフランスの属領だったところ、今でも植民地かな、あそこに行くと原住民たちは〔70「セッタント」、80「ユイッタント」など〕実に合理的にフランス語を変えて使っていますよ」 >> タヒチ(フランス語読み「タイティ」、古くは「オタヘイテ」)島は、フランス保護領(1843年)、オセアニア・フランス植民地(1885年)を経て、1946年、ド・ゴールの「フランス連合」の内部にとどまり、1958年以来、「フランス海外領土」(TOM)です。中心都市はパペーテ。人口は1999年の統計で24万2073人。「海外領土」は「共和国の利益の総体におけるその固有の利益を考慮して、特別の組織を有する」として、「海外県」(DOM)に比べてかなりの自治権が認められています。 >> タヒチの住民(「原住民」よりも「先住民」「現地人」という方が今日では一般的です)は、フランス語とタヒチ語を公用語としていますが、使用されているフランス語は(数詞も含めて)、あくまでもフランス共和国の海外領土としてフランス本土のフランス語とまったく同一です(別頁、タヒチでの数の数え方に関してタヒチ在住の方からのeメールを参照)。 >> 70=septante, 90=nonante が使われているのはスイスとベルギーです。80=huitante(かつてはoctanteも)はスイスの一部の地域で使われます。都知事、ひょっとすると、タヒチでスイスのある特定の地域からいらしたご老人と出会われ、フランス語で相互の年齢でもご確認なさったか・・・? 石原東京都知事――「〔フランス人は、こちらが〕片言のフランス語を話すと知らん顔をしてわからないようなふりをする。」 >> それが「知らん顔」であり、わからない「ふり」であることを、一体どうやって確かめるの? わからないものは、単に「わからない」だけなのでは? 石原東京都知事――「今日ではかなり地方に行きましてもフランス人もまた英語をしゃべらざるを得なくなって、フランス人の非常に頑迷な国民性もだいぶ変わってまいりました。」 >> 国民性なるものは(そういうものが本当に存在するとして)、どこでも多かれ少なかれ「頑迷」なものだから、「・・・性」と呼ばれるのでは? それが、媒介語、道具としての英語を話すようになったくらいで、そんなに易々と変わるものなの? そもそも、自分の国(地域)の言葉に誇りを持つこと、それを大切にしたい、大切にしてほしい、と思うことが、「頑迷」の名に値することなの? 石原東京都知事――「都立大にはドイツ語やフランス語の教員はいっぱいいるのに学生は数人またはゼロ。」「調べてみたら、〔東京都立大学には〕8~9人かな、10人近いフランス語の先生がいるんだけど、フランス語を受講している学生が1人もいなかった。」 >> 調べてみたら、旧・東京都立大学において、フランス語を学ぶ学生は、毎年、数百人(延べ数で千人超)の規模で存在し(平成15年度、延べ1019名)、人文学部フランス文学専攻に在籍する学生の数(昼間部・夜間部の上限定数、各学年それぞれ9名・3名)がゼロであった年度は一度もなかった。大学院をあわせて、常時、数十名の学生がフランス語を専攻していた(平成15年度に学部(2~5年)29名、大学院22名)。 >> 2005年4月に発足した首都大学東京でも、1年生304名(延べ656名)がフランス語を選択し、2年生以上の学生(旧大学在籍)延べ220名が中級以上のフランス語を継続している。 >> 旧・東京都立大学におけるフランス語の専任教員数は、もっとも多い時で12名(英語31名、ドイツ語18名に対して)。以来、6名が他大学へ転出、1名が退職して、現在5名。首都大学東京には、うち4名が就任を承諾し、人員配置の完成時には2名になる予定であるという。都立四大学の統合により、入学定員も1・5倍に増え、それにともなって増加したフランス語のコマ数、流出した専任教員の担当分は、結局、非常勤講師によってまかなわれているという。 石原東京都知事――そういう言葉にしがみついている手合いが〔東京都立4大学の廃止と新大学の設立案に〕反対のための反対している。笑止千万だ。 >> 旧・都立大の仏文の先生方が東京都に対して最後まで諦めずに主張したのは、国際都市東京都の新大学たるもの、フランス語を中心に学ぶ学部専門コースから、フランス、フランス語圏に関する博士論文の指導、受理、審査まで、責任を持って担当することのできる部局を、どんなに小規模でもよいから備えていても不思議はない、という点であったらしい(大学院の専攻課程には最低5~6人のしかるべき専門家がそろっていなければ、その資格がないのだそうだ)。 石原東京都知事――「先進国の東京の首都大学で語学に対する学生たちの需要というのも、フランス語に関しては皆無に近いということは、残念だけじゃなしに、フランスもそういう事実というものを認めて・・・。」 >> 実数にして数百人、延べ数にして1000人以上がフランス語を受講しているのに「一人もいない」とは、いやはや、なんとも気前の良い「切り捨て」計算。そもそも、日本全体のフランス語需要のなかで、「先進国の東京の首都大学」に限りそれが「皆無に近い」とは、これまた一体なぜ?(以下、「ルッソン 5 日本ではどのくらいの人々がフランス語を学んでいるか?」を参照) しかも、フランスが(もっぱらフランスだけが)その「事実」とやらを認めなければならないのは、一体なぜ?  >> やっぱり、ちゃんと勉強しましょうね。フランス語使用、フランス語教育の現在。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルッソン 1 : 60+10、4×20の由来――英語にもあった20進法 ではまず、昨今話題騒然の「数」のお話から。 ベルギー、スイス(タヒチではなく)のフランス語における「セッタント、ユイッタント、ノナント」の使用については先述のとおり。では、ベルギー、スイスのフランス語とまったく同様、大部分ラテン語を基礎としているはずのフランスのフランス語において、ラテン語の septuaginta, octoginta, nonaginta が継承されなかったのはなぜか? 実は、中世からずっと、17世紀、アカデミー・フランセーズによるフランス語の規格化を経たあともなお、18世紀、あるいは19世紀の初頭まで、フランスのフランス語でも、septante, huitante, nonante という数詞は用いられておりました。
しかし、それと平行してケルト起源といわれている20進法も頻繁に用いられておりました。
簡単に言えば、その起源以来、フランス語は10進法と20進法を併用していたわけですな(20進法にもとづく数詞は、フランス語だけでなく、バスク語、ブルトン語、デンマーク語でも採用されていますし、コーカサス地方の一部の言語にも例が見られるそうです)。 ところで皆さん、南北戦争の最中の1863年,ペンシルヴェニア州ゲティスバーグで行われたリンカーン大統領の有名な演説を御存知ですか? そう、あの「人民の、人民による、人民のための政治」という名文句で締めくくられている「ゲティスバーグ演説」。アメリカの子供たちが「独立宣言」と一緒に暗誦させられる、あの演説です。「どう? この中で、アメリカに『NO!』と言ってみたことのある人、いる? 手を挙げてごらん? じゃ君さ、あの演説の冒頭部を英語で言ってごらん。」
はい、よくできました。 ここで、scoreは「点数(スコア)」という意味ではなく、単に古英語の「20」であり、4×20=80、プラスseven years ago で、要するに「87年前」といっているのです。「それじゃあ、君さ、そうそう、同じ君。1863マイナス87は? そう、1776、アメリカ独立の年だよね。」 寺澤芳雄編『英語語源辞典』には、「スコア」は「英語でははじめ「20」の意味に用いられた。この意味は、羊などを数えるのに棒きれに20ずつ切れ目をつけたことから生じたのであろう」という語源解説が引用されています。  結局、60秒が一分、60分が一時間、24時間が一日、7日が一週間、12個が一ダース、6尺が一間・・・と言っているように、何かを数えたり計ったりするに際しては10進法以外の「進法」の方が馴染む、便利、とされた文化があった(そして今もある)ということ、そして、「8×10+7」と言うよりも「4×20+7」と言った方が、「さすが、リンカーン様じゃ」とされた時代があったということです。「一時間半」よりも「90分」と言った方がいい時もあれば、「45日」よりも「一ヶ月半」と言った方がわかりやす時もある・・・。「考えてみれば、「10」の根拠だって、両手の指の数という偶然にすぎないのかもしれず、足の指まで入れれば「20」だって根拠になるじゃあありませんか。キリスト教の世界には、三位一体の「3」と四枢要徳の「4」を組み合わせた面白い7進法と12進法の文化もあるほどです。 結局、60秒が一分、60分が一時間、24時間が一日、7日が一週間、12個が一ダース、6尺が一間・・・と言っているように、何かを数えたり計ったりするに際しては10進法以外の「進法」の方が馴染む、便利、とされた文化があった(そして今もある)ということ、そして、「8×10+7」と言うよりも「4×20+7」と言った方が、「さすが、リンカーン様じゃ」とされた時代があったということです。「一時間半」よりも「90分」と言った方がいい時もあれば、「45日」よりも「一ヶ月半」と言った方がわかりやす時もある・・・。「考えてみれば、「10」の根拠だって、両手の指の数という偶然にすぎないのかもしれず、足の指まで入れれば「20」だって根拠になるじゃあありませんか。キリスト教の世界には、三位一体の「3」と四枢要徳の「4」を組み合わせた面白い7進法と12進法の文化もあるほどです。ちなみにフランス語では一週間のことを「8日間」といいます。ありゃ、これはまずいかな? 今度は「一週間の日数も数えられない言語だ」なんて言われちゃいそう・・・。しかし、これだって、月曜日から月曜日までと考えれば、「足かけ8日間」。その度に人生が1日長くなるわけです。 さて、話を戻してフランスの17世紀、ヴォージュラ、メナージュなど、アカデミー・フランセーズの面々が中心となって、フランス語の統一、規格化作業に着手した際、60までは10進法、70から99までは20進法という現在の体系が正規の語用として採用されました。厳密にいうと、「69」までは20進法が駆逐された、ということですね。なぜ、そのような中途半端なことを?という問いに対しては、はっきりした答えは見出せません。とにかく、そう決めた人々にとって、70以上については「セッタント」よりも「ソワサント=ディス」、「オクタント」「ユイッタント」よりも「カトル=ヴァン」方が「一般的である」と思われたにちがいありません。ひとつの言語を深く研究したことなどない人でも、言葉におけるイレギュラー性が、人の好み、その場の多数決、「一般的」なるもののとらえ方、言い易さ、他の単語との関係など、恣意、偶然としか言いようのないものに左右されるものであるという点は、そう無理もなく理解できるのではないでしょうか(たとえば、nonanteという言葉は、どうしても「修道院の尼さん」nonnainという戯語を連想させてしまいます)。  ちなみに、その後、歴代アカデミー・フランセーズ編纂のすべての辞書に、septante, octante, nonante という、ラテン語から導き出された10進法にもとづく数詞もきちんと登録されている、ということもつけ加えておきましょう。 ちなみに、その後、歴代アカデミー・フランセーズ編纂のすべての辞書に、septante, octante, nonante という、ラテン語から導き出された10進法にもとづく数詞もきちんと登録されている、ということもつけ加えておきましょう。1945年、ナチス・ドイツ占領から解放された直後、フランス共和国臨時政府の文部省は、部分的な20進法をやめて、「セッタント」「ユイッタント」「ノナント」の完全10進法を採用すべきである旨、提言したこともあったそうですが、この時はうまく行かなかったようです。結局は「慣れの問題」ということで、無理な「押しつけ」はかえって混乱の種になると考えられたためでしょう。御上が決めても、一般の人々が使わなければどうにもならないものですからね、言語というのは。ましてや、どこか余所の「先進国」の首都の長が、「合理化の努力をすべき」などと口を挟む筋合いのものでないことはたしかでしょう。少なくとも、かねがね石原都知事がご心配なさっているように、「科学技術の討論をしたり、協定したりするときに非常に厄介」という問題は生じていないようですので、ご安心を。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルッソン 2 : フランス語を使用している国と地域  「フランス語圏国際組織」ホームページ http://qatarfrancophonie.free.fr/cartfranc.html より
(ここに掲げられた国は、あくまでも「フランス語圏国際組織」加盟している国にすぎません。たとえば1830年から百何十年もフランスの植民地とされたアルジェリアは含まれておらず。http://rolrena.club.fr/Francophonie.phpを参照) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルッソン 3 : 「フランコフォニー」(フランス語圏、フランス語使用、フランス語を話すこと)の簡単な年譜
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルッソン 4 : 一体、世界のどのくらいの人々がフランス語を使っているのか?  ならば、現在、地球上に住む約65億人の人々のうち、一体、何人がフランス語を使用しているのか? たしかに、フランス語を「公用語」として用いている国や地域の人口を足し算していくことはできますが、「通用語」として認めている国の人口についてはそうはいきません。フランス語が「通用語」として認められていない国や地域(たとえば日本)にも、いうまでもなくフランス語使用者は存在します。ある言語を「使用する」というのが一体どういう状況を指すのか、定義も定かではありません。ある国のある町で、ホテルでも市場でもフランス語が通じたからといって、その町の住民全員をフランス語使用者とみなすことは到底できない相談です(実際には、その程度の調査によって「○○語使用者」の数がはじき出されているケースもあると聞きますが)。 ならば、現在、地球上に住む約65億人の人々のうち、一体、何人がフランス語を使用しているのか? たしかに、フランス語を「公用語」として用いている国や地域の人口を足し算していくことはできますが、「通用語」として認めている国の人口についてはそうはいきません。フランス語が「通用語」として認められていない国や地域(たとえば日本)にも、いうまでもなくフランス語使用者は存在します。ある言語を「使用する」というのが一体どういう状況を指すのか、定義も定かではありません。ある国のある町で、ホテルでも市場でもフランス語が通じたからといって、その町の住民全員をフランス語使用者とみなすことは到底できない相談です(実際には、その程度の調査によって「○○語使用者」の数がはじき出されているケースもあると聞きますが)。『英語を学べばバカになる』(光文社新書、2005年)の著者、薬師院仁志氏がいみじくも述べておられるように、たとえ英語を公用語、準公用語として掲げている国が世界中にたくさんあったとしても、識字率、公教育の普及率という峻厳なる現実を考慮に入れるならば、「英語使用者」としてその国の人口を計上することはできないわけです。同じことはフランス語についても言えるでしょう。 しかし、「実数がつかみにくい」「定義が曖昧である」とばかり言っていてもはじまりませんから、フランスの雑誌『ヌーヴェル・オプセルヴァトゥール』(2005年3月20日号)から、最新の話題をちょっと拾い出してみましょう。
先に述べた理由により、1億7千500万という数字をあくまでも概数としておさえておくことにいたしましょう。英語、中国語、アラビア語、スペイン語、ロシア語が何億何千万であって、それとの比較においてフランス語はどうなのか、という議論もここではやめておきましょう。なにしろ、それぞれについて億単位で異なる数値がさまざま出されていますし、別々に取られた統計数値を比較することほど無意味なことはないからです。われわれとて、日本の人口1億2千数百万であることは知っていても、「日本語使用者」の正確な数となると・・・? 旧・東京都立大仏文のある先生が書いていらっしゃいます。
そのとおりだと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルッソン 5 : 日本ではどのくらいの人々がフランス語を学んでいるか?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ルッソン 6 : 石原都知事仏語発言に関する海外メディアの反応
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 (用例)
(用例)  (用例)
(用例)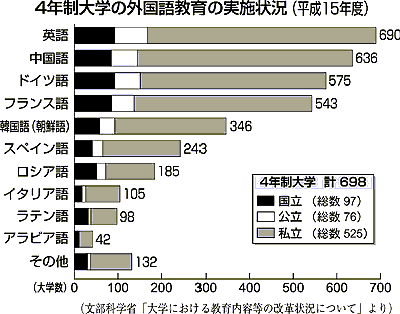
 2002年に行われた別の統計調査結果があります。日本全国660大学にフランス語教育に関するアンケートを依頼したところ、400大学から回答があり、うち80大学は「フランス語を教えていない」という返事だった。つまり320大学からのデータは揃っているわけですが、
2002年に行われた別の統計調査結果があります。日本全国660大学にフランス語教育に関するアンケートを依頼したところ、400大学から回答があり、うち80大学は「フランス語を教えていない」という返事だった。つまり320大学からのデータは揃っているわけですが、